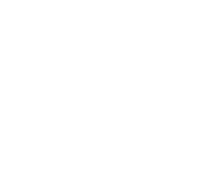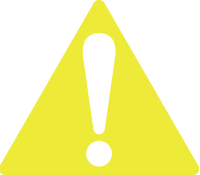ブログ 船橋市の馬込霊園前にある総合供養サービス企業「いしとも」のブログです。
- 千葉県船橋市のお墓・葬儀・仏壇/仏具『いしとも』
- ブログ
- 回忌法要の服装とマナー:これであなたも心配なし!
回忌法要の服装とマナー:これであなたも心配なし!
 回忌法要は、故人を偲び、ご供養するための大切な儀式です。
回忌法要は、故人を偲び、ご供養するための大切な儀式です。
しかし、「どんな服装で行けばいいの?」「マナーに自信がない…」と、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。今回は、回忌法要に参列する際の服装の基本から知っておきたいマナーまで、ブログ形式でわかりやすく解説します。この記事を読めば、落ち着いて法要に臨めるはずです。
回忌法要とは?
回忌法要とは、故人が亡くなった「祥月命日(しょうつきめいにち)」にご遺族や親族が集まり、読経や供養を行う仏事です。
一周忌(三回忌の前)から三十三回忌など節目ごとに行われるのが一般的で、年数が進むにつれ、次第に規模を縮小することも少なくありません。
とはいえ、どの回忌であっても、故人を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な機会であることに変わりはありません。
回忌法要の服装:基本は「喪服」
回忌法要に参列する際の服装は、**原則として喪服(ブラックフォーマル)**が基本です。
ただし、回忌の年数や地域、ご遺族の方針によって、ややカジュアルな装いが許容される場合もあります。
■ 一周忌・三回忌までは「準喪服」を
故人の死後まだ日が浅い一周忌や三回忌は、格式ある場とされるため、準喪服での参列が望ましいとされています。
男性:
- ブラックスーツ(礼服)
- 白いワイシャツ
- 黒のネクタイ(無地)
- 靴下・靴も黒が基本
- ネクタイピンや派手な時計は避けましょう
女性:
- 黒のワンピースやアンサンブル、パンツスーツなど
- 肌の露出を控えたデザインが望ましい
- 黒のストッキング(肌色でも可)を着用し、生足は避ける
- 靴・バッグともに黒のシンプルなもの(布製やマット素材が無難)
- アクセサリーは一連のパールネックレス程度。結婚指輪は着用可
■ 七回忌以降は略喪服でも可
時間の経過とともに、服装もやや柔軟になります。七回忌以降では、略喪服や地味な平服でも失礼にはあたりません。
男性:
- 黒・濃紺・濃いグレーなどのダークスーツ
- 白シャツと地味なネクタイ(黒または落ち着いた柄)
- 黒の靴・靴下が基本
女性:
- 黒・グレー・紺など控えめな色合いのワンピースやスーツ
- 華やかなデザイン・露出の多い服装は避ける
- 靴やバッグも落ち着いたものを選び、装飾を控える
【迷ったら…】
不安な場合は、一周忌や三回忌と同様の準喪服で参列すれば間違いありません。
地域や宗派、またご遺族の意向によって多少の違いがあるため、事前に確認できるとより安心です。
回忌法要でのマナー:心構えと振る舞い
服装以外にも、回忌法要には心得ておきたいマナーがいくつかあります。
■ 香典(御仏前)の準備
回忌法要では、**「御仏前」**と表書きした香典を用意します。
四十九日までは「御霊前」とされますが、それ以降は「御仏前」が一般的です。
- 金額の目安は1万~3万円(故人との関係や地域差、会食の有無による)
- 香典袋は黒白または双銀の水引、結び切りを選ぶ
- 新札は避けつつ、あまりに汚れたお札も控えましょう
なお、宗派(浄土真宗など)によっては「御仏前」を使用せず、「御香資」などを用いる場合もあるため、可能であれば確認しておくと安心です。
■ 数珠は持参を
仏式の法要では、数珠(じゅず)は仏前に対する敬意を示すものです。
宗派によって多少形状が異なりますが、基本的には自身の宗派のものを一つ用意しておくと安心です。
- 手に持って読経に合わせて合掌
- 座っている間は左手にかけるか、膝上や座布団の上に置く
■ 時間厳守で行動を
法要は定刻で始まることが多く、遅刻は失礼にあたります。
10〜15分前には到着し、受付を済ませて静かに着席しましょう。
もしやむを得ず遅れる場合は、事前に連絡を入れることが最低限の礼儀です。到着後は、後方から静かに入室するなど、配慮を忘れずに。
■ 携帯電話と私語は慎む
法要中は、携帯電話の電源をオフまたはマナーモードにし、通知音が鳴らないように注意しましょう。
また、私語は慎み、厳粛な雰囲気を保つよう心がけることが大切です。
■ 思い出を語る場では節度を持って
法要後の会食では、故人を偲んでの思い出話などが自然な流れです。
笑顔も時にご供養となりますが、羽目を外しすぎず、節度ある言動を意識しましょう。
まとめ
回忌法要は、故人を偲び、ご遺族とともにその想いを分かち合う大切な場です。
服装やマナーに不安を覚えることもあるかもしれませんが、基本を押さえておけば問題ありません。
なによりも大切なのは、故人を思う気持ちと、ご遺族への心配りです。形式にとらわれすぎず、誠意ある態度で臨むことが、最も尊い供養につながります。