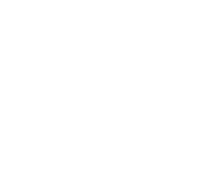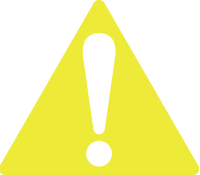ブログ 船橋市の馬込霊園前にある総合供養サービス企業「いしとも」のブログです。
- 千葉県船橋市のお墓・葬儀・仏壇/仏具『いしとも』
- ブログ
- 葬儀前の故人対面について:注意点とマナー
葬儀前の故人対面について:注意点とマナー
最後の時間を穏やかに、敬意をもって
大切な人との別れは、人生の中で最も心を揺さぶられる瞬間の一つです。突然の訃報に接し、言葉を失うような衝撃を受けたとき、私たちは「何かできることはなかったか」と自問し、深い喪失感の中で故人を偲びます。
葬儀や通夜の前に故人と対面することは、そうした深い悲しみのなかで、故人と静かに向き合い、最後のお別れをする貴重な時間です。この機会は、故人への敬意と感謝、そして心の整理をつけるための大切なひとときとなるでしょう。
本稿では、「葬儀前の故人対面」に際しての基本的なマナーや注意点、そして心構えについて詳しく解説します。故人やご遺族への思いやりを形にするために、ぜひご一読ください。
葬儀前の故人対面とは
通夜・葬儀が執り行われる前に、ご自宅や葬儀社の安置施設などで、故人と直接顔を合わせることを指します。
この対面は、喪主や近親者の同意を得たうえで、限られたご親族や親しい友人、故人と深い関わりのあった人にのみ許されることが多く、一般の弔問とは少し趣が異なります。
場合によっては、納棺前の「納棺の儀」や、出棺直前の「最後のお別れの時間」といった節目の場面と重なることもあります。
この機会は、単なる形式的な弔意表明ではなく、故人との対話を心の中で交わし、感謝の気持ちを伝えるための、かけがえのない時間なのです。
対面時の一般的な流れ
1. 訪問前の準備と連絡
- 故人との対面は、喪主をはじめとしたご遺族のご厚意によって成り立っています。そのため、訪問前には必ずご遺族に連絡し、許可と訪問のタイミングを確認することが何よりも大切です。
- 連絡の際には、以下のような丁寧な表現が望ましいでしょう。
- 「突然のことで驚いております。ご迷惑でなければ、故人様にお目にかからせていただきたいのですが、ご都合のよろしい時間帯はございますでしょうか」
- 遺族の心身は疲弊していることが多いため、連絡は手短に済ませ、長電話は避けましょう。
2. 訪問・挨拶
- ご自宅や施設に到着した際は、まずはインターホンや玄関先でご遺族に丁寧にご挨拶をします。
- 「本日はご無理を申し上げて申し訳ありません。お時間をいただき、ありがとうございます」
- 上着(コートなど)は玄関で脱ぎ、部屋に持ち込まないよう注意します。
3. 故人との対面
- ご遺族の案内に従って、故人が安置されている部屋へと静かに入室します。
- 部屋に入る際には、「失礼いたします」と一言添えてから静かに入りましょう。
- カバンは邪魔にならないように置き、故人に正対して、合掌あるいは黙祷を捧げます。
- 故人の顔に布がかけられている場合、ご遺族が布を外してくださるまで待ちます。触れることは基本的に控えますが、もし自然に促される場面があれば、必ずご遺族の許可を得てからそっと手を添えましょう。
- 声に出す言葉は控えめに。心の中で「ありがとうございました」「安らかにお休みください」と語りかけるのが適切です。
4. お別れと退室
- 最後のお別れを終えたら、ご遺族に向き直って一礼し、「心よりお悔やみ申し上げます」と一言添えて退室します。長くとどまることは避け、速やかに辞去するのが望ましいです。
- 故人対面時の服装と身だしなみ
喪服でなくてよい場合も多いですが、黒・紺・グレーなど、落ち着いた色合いの平服を選びましょう。 - 過度に華美な服装や香水は避けるのが礼儀です。
- アクセサリーは結婚指輪を除いて外すのが一般的。
- 靴は清潔なものを選び、玄関で丁寧に脱ぎ揃えましょう。
ご遺族への配慮
- お悔やみの言葉は慎重に
「ご愁傷様でございます」「このたびは誠に…」といった言葉を、静かに短く述べます。 - 励ましやアドバイス、慰めの言葉は控えめに。
「頑張ってください」「元気出してくださいね」といった表現は、時としてご遺族を傷つけてしまうことがあります。 - 忌み言葉を避ける
重ね言葉(再び、繰り返し、度々など)は避け、「死ぬ」「生きる」など直接的な表現は使用しません。
例:
×「死んでしまって残念です」
○「ご逝去を悼み、心よりお悔やみ申し上げます」
写真撮影について
- 近年、スマートフォンで写真を撮る人が増えていますが、故人の安置場所での撮影は厳に慎むべき行為です。特にSNSなどに投稿するなどは言語道断です。
- 写真を撮る必要がある場合でも、ご遺族の許可なく行ってはいけません。
長居は無用
- 故人と対面したあとは、なるべく早めに辞去しましょう。たとえ親しい間柄であっても、ご遺族は多くの対応に追われている場合があります。
- ご遺族に「何かお手伝いできることがあればおっしゃってください」と一声添えるのは丁寧ですが、無理に関わろうとしないことが大切です。
状況別の配慮
特に親しい間柄の場合
幼なじみや旧友など、深い関係にある場合は、思いが溢れて涙が止まらないこともあるでしょう。それでも、ご遺族が気を使ってしまわないよう、感情のコントロールを心がけることも礼儀の一つです。
遠方からの弔問の場合
宿泊や移動手段については自分で手配し、ご遺族に負担をかけないように配慮します。また、お香典のタイミングや渡し方なども、事前に確認しておくと安心です。
故人との最後の時間を、大切に
葬儀前の対面は、故人との絆を確かめ、心の中で別れを告げるとともに、ご遺族に対して寄り添う時間でもあります。
そこに必要なのは、形式や流儀ではなく、「心からの敬意」と「思いやりの気持ち」です。
穏やかな気持ちで、静かに故人を見送り、その人生に感謝と祈りを込める——その姿勢こそが、最も美しい弔いのかたちなのかもしれません。