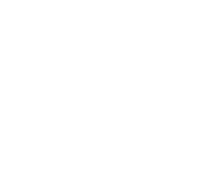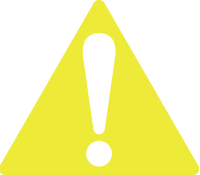ブログ 船橋市の馬込霊園前にある総合供養サービス企業「いしとも」のブログです。
- 千葉県船橋市のお墓・葬儀・仏壇/仏具『いしとも』
- ブログ
- 初めてのお墓参りガイド|意味・手順・マナー・持ち物までわかりやすく解説
初めてのお墓参りガイド|意味・手順・マナー・持ち物までわかりやすく解説
 お墓参りの経験があっても、自分が中心となって行うのは初めて、という方も多いのではないでしょうか。この記事では、お墓参りの意味や基本的な手順、持ち物、時期、宗教別の作法、そしてマナーまで、初めての方にもわかりやすくご紹介します。
お墓参りの経験があっても、自分が中心となって行うのは初めて、という方も多いのではないでしょうか。この記事では、お墓参りの意味や基本的な手順、持ち物、時期、宗教別の作法、そしてマナーまで、初めての方にもわかりやすくご紹介します。
お墓参りとは何か
お墓参りは、故人やご先祖様に手を合わせ、感謝や冥福を祈る供養の行為です。お墓は、亡き人とのつながりを感じられる心の拠り所ともいえます。
お墓参りを通じて、命をつないでくれたご先祖様への感謝の気持ちが自然と生まれ、見守られている安心感を得られる方も多いでしょう。
お墓参りの基本:何をするのか
お墓参りに明確な決まりはありませんが、基本的な供養は以下の「五供(ごく)」をお供えすることと、手を合わせることです。
線香
花
灯明(ろうそく)
水
食べ物(果物・お菓子など)
ただし、宗教・宗派や家ごとの習慣によって異なる場合があるため、不安な場合は親族や菩提寺に相談するのが良いでしょう。
お墓参りに適した時期
お墓参りには厳密な決まりはありませんが、一般的に多くの人が訪れる時期をご紹介します。
お盆(7月または8月)
もっとも多くの人が訪れる時期。ご先祖様が家に帰ってくるとされるため、初日にお迎えに行く意味もあります。
7月盆:7月13日~16日(東京など一部地域)
8月盆:8月13日~16日(全国的に多い)
お彼岸(春分・秋分)
春と秋、年2回あるお彼岸もお墓参りの定番です。
春彼岸:春分の日を中心とした7日間(3月)
秋彼岸:秋分の日を中心とした7日間(9月)
昼と夜の長さが等しくなるため、あの世とこの世が近づく時期と考えられています。
命日
祥月命日:故人が亡くなった月日(年に1回)
月命日:亡くなった日(年11回)
毎月行く方もいますが、一般的には祥月命日にお参りをします。
年末年始
年末:1年の感謝を伝える
年始:新年の挨拶をする
帰省のタイミングでもあり、親族が揃いやすいため、まとめてお参りを行うケースもあります。
時間帯はいつがよい?
理想は午前中
混雑も少なく、気温も低め。清々しい気持ちで掃除・供養ができます。
午後でも明るいうちに
日が長い季節であれば夕方でも構いませんが、暗くなる前に済ませましょう。
お墓参りに必要な持ち物一覧
持ち物 用途
ほうき 墓地周辺の掃除
軍手 草むしりや清掃時の保護
ゴミ袋 雑草やゴミを持ち帰るため
バケツ 掃除用の水を汲む
雑巾 墓石を拭く
たわし コケ・汚れを落とす(金属製は避ける)
手桶・ひしゃく 墓石に水をかけるため(霊園で借りられる場合も)
線香 供養の基本
花・お菓子 故人の好物などをお供え(お菓子は持ち帰る)
お墓参りの手順
手を洗い清める
水を汲んでお墓へ向かう
墓前で一礼し、掃除をする
雑草の除去 → 掃き掃除 → 墓石の清掃(たわし・雑巾・歯ブラシなど活用)
線香・花・供え物を供え、手を合わせる
食べ物などはそのままにせず、必ず持ち帰りましょう。
宗教ごとの作法の違い
仏教(宗派により異なる)
線香の本数・折るかどうか・立て方などが異なります。
例:浄土真宗では線香を寝かせて供える。
神道
線香ではなく「榊」や「玉串」を供える。
供え物:酒、米、塩、水など(神饌)
キリスト教
お墓参りは重視されず、神に祈りを捧げる形。
お供えは白い花(例:カーネーション)など。
お墓参りのマナー
服装は落ち着いたものを
法要がなければ喪服は不要ですが、華美すぎない服装が望ましいです。
花は仏花(菊など)を選ぶ
棘のある花(バラなど)や香りが強すぎる花は避けましょう。
霊園のルールを守る
開園時間・火気・供え物の取り扱いなどを事前に確認しましょう。
参拝の順番に配慮を
故人と縁の深い順(例:配偶者 → 親族 → 友人)で手を合わせるのが一般的です。
まとめ
お墓参りは、形式にとらわれすぎる必要はありませんが、感謝の気持ちと礼儀をもって行うことが何より大切です。宗教や家庭のしきたりに配慮しつつ、できる範囲で心を込めて故人を偲びましょう。